「今回のテスト、全然できなかった……」「もっと早くから始めればよかった」。
こんな後悔、毎回のようにしていませんか?
定期テストは、内申点に直結する大事な節目。
中学生にとって、テストの点数がそのまま将来の選択肢に影響すると言っても過言ではありません。
しかし、いざ勉強となると「いつから」「どれくらい」「どうやって」やればいいのか、意外と明確な基準がないのも事実です。
このコラムでは、中学生が定期テストで成果を出すために必要な勉強の考え方と実践方法を、具体的にご紹介します。
目次
テスト勉強はいつから始めるべき?理想的な準備期間とは

「テスト週間」だけがテスト対策期間だと思っていませんか?
実際、多くの学校ではテスト1週間前に“部活動停止”となることで、いわゆる“テストモード”に入ります。
ですが、本当に効果的な対策をしたいのであれば、2週間前からのスタートが最適です。
なぜ2週間前がベストなのか?
1週間だけの勉強では、以下のような問題が生じやすいです。
- 暗記が間に合わない
- 苦手分野を見つけても復習する時間がない
- 提出物やプリント整理に追われて本番対策できない
逆に、2週間前から始めれば、以下のような余裕が生まれます。
- 勉強の全体像をつかめる
- 復習→演習→確認のサイクルを確保できる
- 時間に追われず、焦りが少なくなる
テスト範囲が未発表でも、授業ノートや教科書を見れば予想はつくはずです。「今週の授業内容をすぐに軽く復習しておく」だけでも、後のテスト勉強がぐっと楽になります。
計画の基本は「逆算思考」
2週間前に始めるには、テスト本番から逆算して勉強計画を立てることが重要です。
- 各教科の範囲を予想・確認
- 単元ごとに必要な勉強量を見積もる
- 「何日に何をやるか」をスケジュール化
この「スケジュール作成」こそが、効率的なテスト勉強の土台となります。
1日どれくらい勉強すればいい?学年別・時期別の目安時間
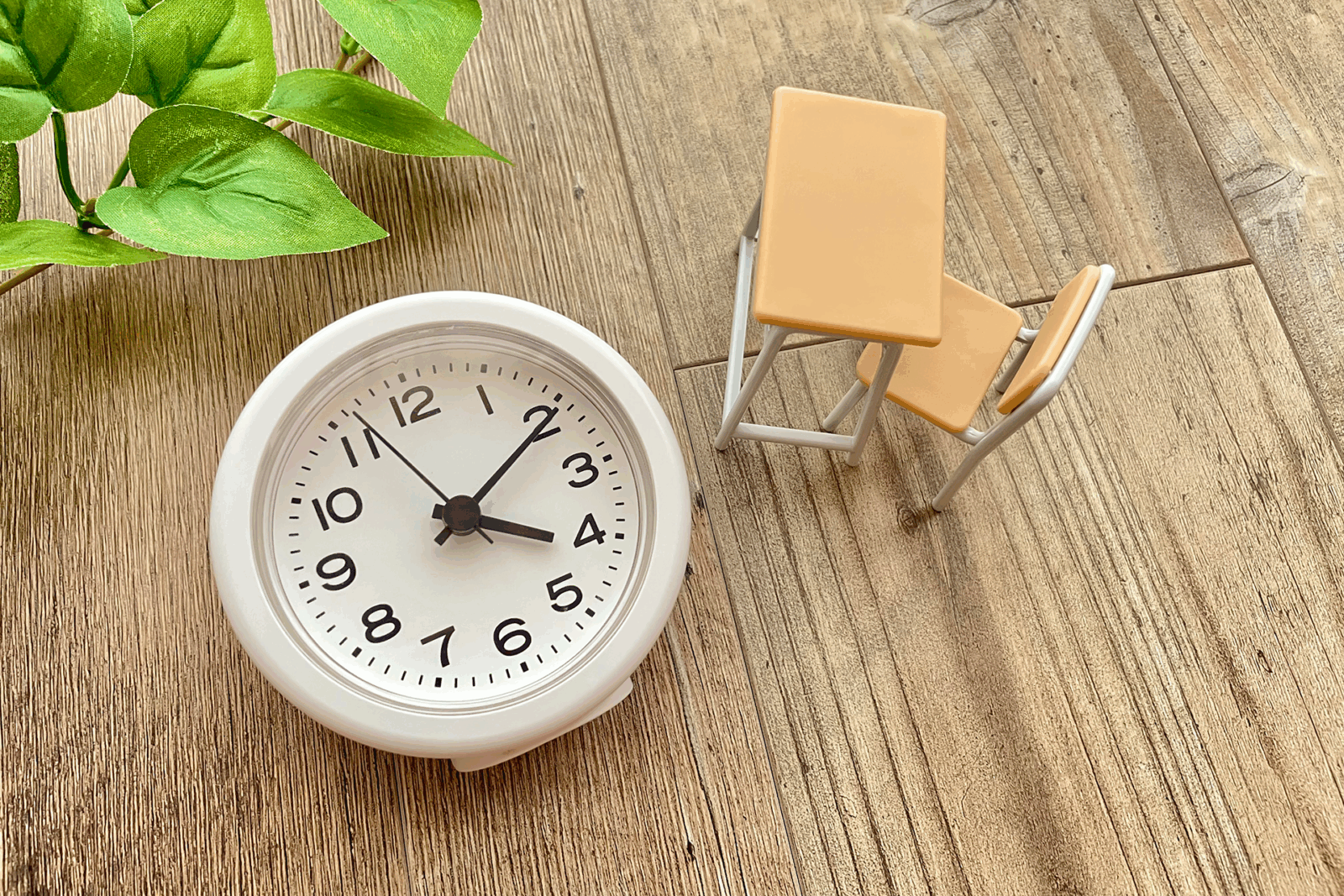
「部活や習い事もあって時間がない」「毎日同じように勉強できない」。
こうした中学生の生活リズムを考慮すると、“集中できる時間をどう確保するか”がポイントです。
テスト前の学年別・時期別の勉強時間目安
| 学年 | テスト2週間前 | テスト1週間前~直前 |
| 中学1年生 | 1~1.5時間 | 2~2.5時間 |
| 中学2年生 | 1.5~2時間 | 2.5~3時間 |
| 中学3年生 | 2~3時間 | 3~4時間以上 |
この時間はあくまで“目安”ですが、重要なのは「時間の長さ」よりも「内容の濃さ」です。
30分でも、スマホを手放して集中して取り組めば、意味のある学習になります。
時間の“質”を高めるために意識したいこと
- 場所の確保:自宅だと誘惑が多い場合は、自習室などを活用
- タイムブロッキング:勉強時間をあらかじめブロックしてスケジュールに組み込む
- ポモドーロ・テクニック:25分集中+5分休憩を繰り返す勉強法で集中力を維持
また、毎日同じ時間帯に勉強する習慣をつけると、体が自然と「勉強モード」になりやすくなります。
定期テストで成果を出すための効率的な勉強法

効率のよい勉強とは、決して「手を抜くこと」ではありません。
限られた時間で、得点につながる部分に集中して取り組む工夫のことです。
ここでは、実践しやすく、成果に直結しやすい方法をいくつかご紹介します。
教科ごとに戦略を立てる
教科によって勉強の方法は異なります。
- 英語・数学:演習と解き直しがカギ
- 社会・理科(暗記中心):図や語呂で記憶をサポート+反復演習
- 国語:教科書の音読+記述問題対策
- 技術・家庭・保健体育など:提出物の精度+ワークの確認
それぞれの科目に合ったアプローチを知っているだけで、無駄な時間を大幅に削減できます。
「理解→定着→アウトプット」の流れを意識する
効率よく覚えるには、以下の3ステップが大切です。
- 理解:教科書やノートを読んで内容を把握
- 定着:ポイントを整理して記憶する
- アウトプット:問題演習で思い出す練習をする
特にアウトプット(問題を解くこと)は記憶を深める上で非常に効果的です。
テスト範囲のワークや学校のプリントを繰り返し解い、「自分で使える知識」に変えることが重要です。
自分の“弱点”に向き合う
テスト勉強は「できるところ」だけやっていても伸びにくいです。
- 間違えた問題をノートにまとめる
- 解説を読んでもわからない問題は先生や友人、自習室スタッフに質問
- 苦手な単元は小さく区切って取り組む
特に、「毎回同じような問題で間違える」「ケアレスミスが多い」という人は、自分の弱点を分析して対策を練ることが得点アップの近道です。
自習室や静かな環境を積極的に活用する
家での勉強は、テレビ、スマホ、家族の会話など、集中を妨げる要素が多くあります。
当自習室のように、“勉強するための空間”が整った場所を利用することで、学習効率は格段にアップします。
- 周囲も静かに勉強しているので、自分もやる気が出る
- 時間を決めて通うことで習慣化しやすい
- 自主性が育ち、勉強の自己管理能力が身につく
「誰かに教えてもらう」のではなく、“自分で学ぶ力”を伸ばす場として、自習室を最大限に活用しましょう。
【保護者の方へ】テスト勉強に悩むお子さんを見守るコツ
中学生になると、子ども自身に任せたいと考える保護者の方も多いと思いますが、以下のようなサポートがあると、お子さんも安心して勉強に集中できます。
- 「勉強しなさい」ではなく、「頑張ってるね」「あとちょっとだね」と声かけ
- 過干渉はせずに、勉強環境(静かな時間・場所)を整えてあげる
- 自習室や学習スペースの利用も選択肢として一緒に考える
「応援されている」と実感できるだけでも、やる気は大きく変わるものです。
定期テストに効果的な勉強計画・スケジュールの立て方とは?

「何から手をつければいいのか分からない」「計画を立てても結局守れない」
テスト前になると、そう感じる人は多いのではないでしょうか?
しかし、勉強計画がしっかり立てられているかどうかで、テスト結果は大きく左右されます。
やみくもに勉強を始めるのではなく、「ゴールまでの道筋を見える化」することが、テスト対策の第一歩です。
ここでは、効果的な計画の立て方を具体的な手順で紹介します。
ステップ1:テストまでの「残り日数」を把握する
まずは、テストまであと何日あるのかを正確に確認しましょう。
たとえば、テストまで残り14日(=2週間)あるとしたら、その14日間を「準備期間」「本格的な勉強期間」「仕上げ期間」の3つに分けて考えるのがおすすめです。
- 準備期間(最初の3日程度):テスト範囲の確認、スケジュール作成、教材整理などを行う
- 本格的な勉強期間(中盤の7日間ほど):主要な教科を中心に暗記や問題演習を行う
- 仕上げ期間(直前の4日間):テスト前の総復習や見直し、暗記の最終チェックに集中
このように期間を区切ることで、「今は何をすべきか」が明確になります。
何となく勉強を始めるのではなく、「この時期はこれをやる」と決めておくと、勉強の効率も格段にアップします。
ステップ2:教科ごとの“優先順位”を決める
すべての教科を同じように勉強するのは非効率です。
次のような観点から「どの教科を重点的にやるか」を決めましょう。
- 苦手で点が取れない科目 → 時間を多めに確保
- 得意だけど気を抜くと落としやすい科目 → 毎日少しずつ触れる
- 点数配分が大きい教科 → 配点を意識して対策
- 提出物の有無 → 提出期限から逆算して計画
たとえば、「数学と英語は早めに始めたい」「社会と理科は暗記なので後半に集中して復習したい」など、教科ごとに戦略を立てることがポイントです。
ステップ3:1日ごとの計画に落とし込む
テスト勉強は、最終的に“毎日の行動”に落とし込めて初めて意味を持ちます。
以下のような形で、「いつ・どの教科を・どこまでやるか」を具体化しましょう。
例)テスト10日前のスケジュール
| 時間帯 | 内容 |
| 17:00~17:30 | 国語:教科書の音読+問題集1ページ |
| 18:00~18:45 | 数学:ワークの解き直し(2年方程式) |
| 20:00~20:30 | 英語:単語暗記20個+教科書本文音読 |
| 21:00~21:30 | 社会:地理プリントの赤シート暗記 |
可能であれば、「勉強記録ノート」や「進捗チェックリスト」を作って、毎日実行できたか確認する習慣をつけると、達成感が得られて継続もしやすくなります。
ステップ4:復習と見直しの“余白”をつくる
計画を詰め込みすぎてしまうと、体調不良や急な用事が入ったときに崩れてしまい、やる気も落ちてしまいます。
だからこそ、あえて「何も予定を入れない日」「予備の復習日」を用意しておきましょう。
たとえば、
- 3日に1日は復習中心にする
- 土日は柔軟に使えるように余裕を持たせる
- 前日の復習時間を翌日の計画に入れる
など、“予定が狂ってもリカバリーできる設計”を意識することで、無理のないスケジュールになります。
ステップ5:スケジュールは「完璧」より「継続」を重視
最初から理想的な計画を立てるのは難しいもの。
途中でうまくいかなくても、「ズレたら修正すればいい」くらいの気持ちでOKです。
大切なのは、「毎日、少しずつでも進めている実感」を持てること。
気持ちが続くことで、学習リズムも自然と整っていきます。
計画がうまくいかない人は「場所」と「環境」を変えてみよう
どうしても家では集中できない、自分で計画を守れない……。
そんなときは、当自習室のように「学ぶことに特化した場所」に身を置くのが効果的です。
- 周囲も頑張っている → 勉強スイッチが入りやすい
- 時間が決まっている → ダラダラしない
- 計画に沿った勉強がしやすい → 自分のペースを作れる
計画を立てることは、成績だけでなく、自己管理能力や集中力を伸ばす絶好の機会でもあります。
まずは、明日1日の予定だけでも書き出すことから始めてみましょう。
まとめ
テスト勉強の成功は、早めのスタート・自分に合った勉強法・集中できる環境の3つで大きく左右されます。
「何となく」ではなく「目的をもって」「計画的に」取り組むことが、良い結果につながる最短ルートです。
そして、必要であれば自習室などの環境を利用することも有効な手段です。
まずは、今日の夜からでも始められる「小さな一歩」を踏み出してみてください。


