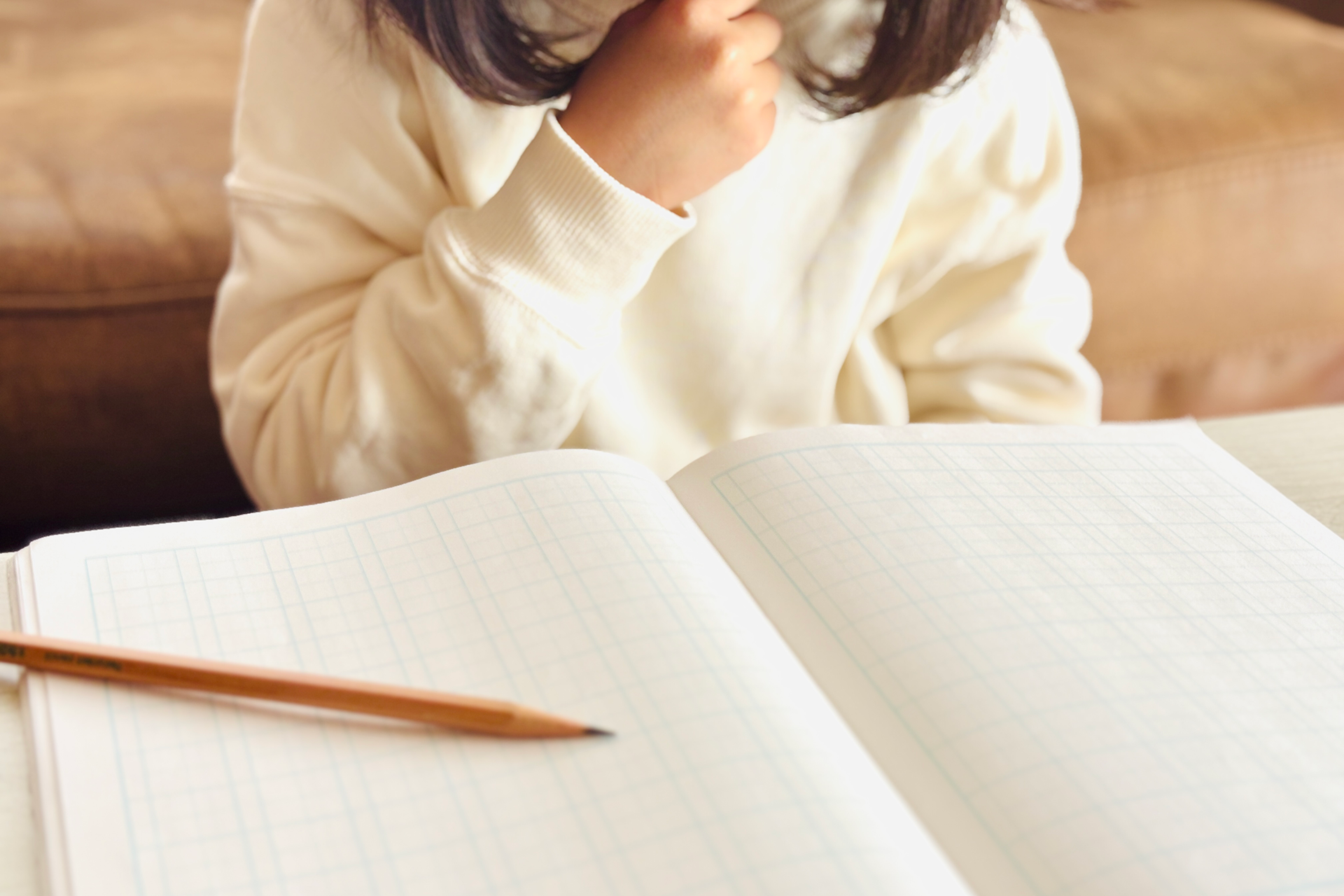「何をしても点数が上がらない」「テストの結果を見るのが怖い」「授業についていけず、何がわからないのかすら分からない」、そんな不安や焦りを感じている中学生は、決して珍しくありません。
特に中学に入ってから成績が急に落ちたと感じたり、5教科すべてに苦手意識を持ち始めた人にとっては、「勉強がわからない」以前に、「勉強って何をどうすればいいの?」という根本的な疑問に直面していることも多いはずです。
自分だけが取り残されているように感じて、友達や先生にも相談できず、「自分には勉強なんて向いてない」とあきらめかけてしまうこともあるかもしれません。
でも、安心してください。それはあなただけではありません。
そして、そこから抜け出す方法は、確かに存在します。
この記事では、5教科すべてが苦手という状態から、少しずつ前進するための具体的な方法を紹介します。
「どこから始めればいいか分からない」というスタートラインに立っているあなたにとって、この記事が次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
目次
なぜ「全部苦手」になるのか?まずは原因を整理しよう
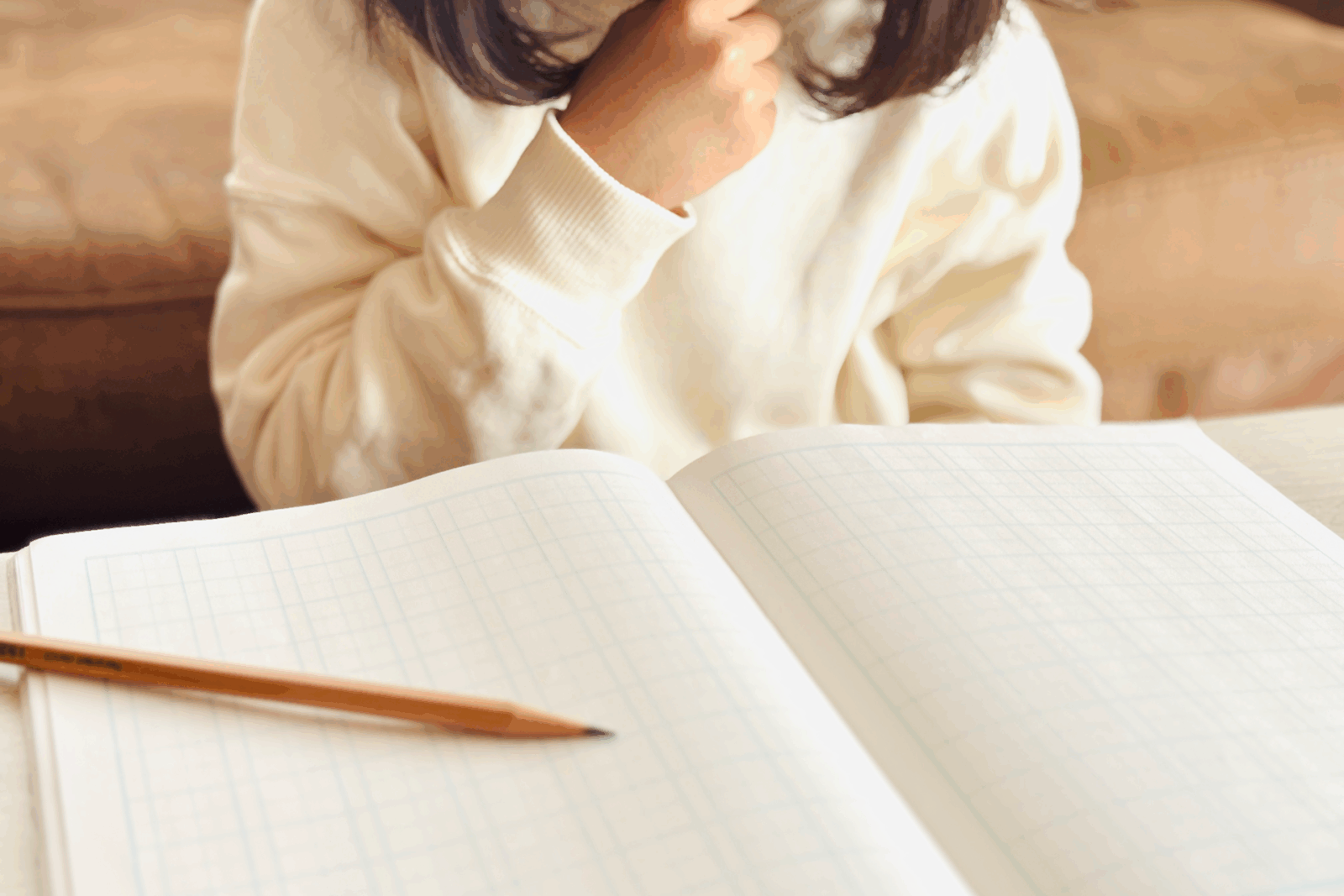
5教科がすべて苦手という状態は、「能力がないから」ではありません。
たいていの場合、以下のような理由が積み重なって苦手意識が強くなっているのです。
- 小さなつまずきを放置してきた
- 勉強のやり方がわからない
- 成功体験が少なく「どうせできない」と思ってしまう
- 自信のなさが苦手意識を強化している
- 勉強時間が確保できていない/集中できる環境がない
まずは「自分がなぜ苦手だと感じているのか?」を紙に書き出してみましょう。
頭の中でぐるぐる考えるだけでなく、言葉にすることで現状が整理され、「じゃあどうするか?」を考える土台ができます。
スタート地点は「得意を探す」ではなく「苦手の中のマシ」を見つけること
全部苦手…と言っても、100点満点中の全教科が10点ということは少ないはずです。
「理科は20点、数学は15点、英語は18点…」というように、点数に微妙な差があることが多いのです。
この小さな差をヒントに、「まだ比較的点が取れている教科」=「苦手の中のマシな教科」から取り組むのがポイントです。
たとえば、
- 英語は単語がわかれば少し解ける
- 理科の暗記系はまだ覚えやすい
- 社会は授業を聞いていてなんとなく面白かった
といった感触があるなら、そこから始めるのが効果的です。
完全に苦手な科目よりも、少しでも手応えのある教科の方が、成果が出るスピードが速く、モチベーションも維持しやすいからです。
「基本に戻る勇気」が最大の武器になる
中学生になると、「こんな簡単なところからやり直すなんて恥ずかしい」と思ってしまいがちです。
しかし、基礎の抜けがあるままでは、どれだけ時間をかけても成績は伸びません。
英語なら「be動詞と一般動詞の違い」、数学なら「分数・小数・割合」、理科なら「用語の意味」、国語なら「主語と述語」「接続語」など、まさに小学校高学年〜中1前半レベルの基本が理解できていないケースが多いのです。
自分の理解度に合ったところから、恥ずかしがらずにスタートすること。
それが、遠回りのようで実は最短ルートです。
教科別の学び直し戦略
ここからは、各教科の「つまずきやすいポイント」と「やり直しの具体的な方法」を解説します。
英語:単語と文法の型を覚えることから
英語の苦手克服には「単語力」と「文の型(文法)」の理解が不可欠です。
難しい文章を読む必要はありません。
- まずは中1の教科書に出てくる単語をノートに書き出す
- 毎日10語ずつ音読&書き取りを続ける
- 文法は「主語+動詞」から、be動詞/一般動詞の文をマスターする
文法書よりも教科書の例文を「そのまま丸ごと覚える」方が実用的です。
数学:計算力と理解の両方が必要
- まずは「正負の計算」や「分数の四則計算」をミスなく解けるようにする
- 基本問題を1冊繰り返し解く(たくさんの問題集に手を出さない)
- 解けなかった問題は「なぜ間違えたか」「どう直すか」を書く習慣をつける
1日10分でもいいので、毎日「ミスの少ない解き方」を意識して取り組むのが効果的です。
国語:読解力は「解き方」で伸びる
- 長文を読んでも意味がわからない場合、まずは「設問」を先に読んでから本文を読む
- 接続語、指示語(これ・それ・あれ)に注目するだけでも理解が変わる
- 教科書の音読を毎日続けると、語彙力・文の構造感覚が自然と身につく
国語は「慣れ」が大きな武器になる教科です。
理科・社会:覚えるコツと繰り返しが鍵
- 覚えるべき語句は「自分なりに図にする」「色分けする」など視覚的工夫をする
- 間違えた問題は「なぜそれが答えじゃないのか?」も一緒に覚えると定着率が上がる
- 教科書→プリント→ワークという順番で繰り返すことで、知識が強化される
暗記ではなく「イメージでつなげる」「流れでつかむ」ように意識してみましょう。
「やる気が出ない」ときにこそ試してほしい、心と行動の整え方

勉強しなきゃいけないのはわかってる。
でも、どうしてもやる気が出ない。
そんな経験、ありませんか? 特に5教科すべてに苦手意識があると、「何をやっても無駄なんじゃないか」「どうせ頑張っても点数は上がらない」と思い込んでしまい、気持ちが前に進まなくなることがあります。
このような状態にあるとき、真面目な人ほど「自分はダメだ」と自分を責めてしまいがちです。
しかし、それではさらに心が疲れてしまい、勉強からますます遠ざかってしまいます。
そんなときは、自分を責めるのではなく、行動と気持ちの「ハードルを思いきり下げる」ことが、意外な突破口になります。
小さく始めることが“やる気”のスイッチになる
「やる気が出ない」状態というのは、何かができないのではなく、“最初の一歩”が踏み出せないだけのことが多いのです。
心理学でも、行動はやる気に先行することがあるとされています。
つまり、「やる気が出たら始める」のではなく、「とりあえず少しだけ始めてみる」ことで、逆にやる気が湧いてくるのです。
たとえば、次のような小さな行動が「やる気の火種」になります。
- とりあえず5分だけ勉強してみる
→ 時間を決めると気持ちが軽くなります。
「5分だけ」と決めることで、思ったより続くことも多いです。
- 教科書を1ページ音読するだけ
→ 声を出すことで脳が刺激され、集中モードに入りやすくなります。
内容が頭に入らなくてもOKです。まずは“動き出す”ことが大切です。
- ペンを持って、今日やることを紙に1行書くだけ
→ それだけでも「やった」という実感が得られます。
やることが明確になると不安が減ります。
これらはほんの一例ですが、ポイントは「目標をできるだけ小さく、簡単にする」ことです。
小さな行動を積み重ねることで、「やる気が出ないから何もしない」という状態を抜け出せる可能性が高まります。
成果よりも「行動したこと」に注目して自分を褒める
テストの点数が良くないとき、「全然勉強しても意味なかった」と感じてしまうことがあるかもしれません。
でも、本当にそうでしょうか? 点数がすぐに上がらなくても、前より机に向かう時間が増えた、ワークを1ページ終わらせた、わからないことを質問できた…こうした行動の積み重ねこそが、本当の意味での「成長」です。
だからこそ、自分の努力をきちんと認めてあげることが重要です。
- 「昨日より5分長く机に向かえた」
- 「ワークの1問だけど自力で解けた」
- 「音読したら少し発音がスムーズになった」
これらはどれも、立派な成果です。
勉強の苦手な自分が、勉強という苦手分野に向き合おうとしている。
それ自体が、ものすごく価値のあることなのです。
まずは、「今日はこれをやった自分、えらい!」と、毎日自分をねぎらう習慣を持ちましょう。
人は「できたこと」を意識すればするほど、次への意欲が生まれやすくなります。
それでもつらいときは、「やらないとき」も受け入れる
ここまで、やる気を出す工夫についてお話してきましたが、それでも「今日は本当に無理…」という日があるかもしれません。
そんなときは、無理に気合で乗り越えようとせず、「今日は休む日」と自分に許可を出してあげることも大切です。
勉強に限らず、気持ちが沈んでいる時は、無理に頑張ろうとすると逆効果になることがあります。
やる気が出ない状態が続くようであれば、信頼できる大人に相談したり、環境を変えてみたりすることも必要です。
休むことでリセットされ、次の日にスッと行動に移れることもあります。
自分を責めずに、長い目で少しずつ前進していきましょう。
「やる気」は毎日育てる“習慣”として育てていくもの
やる気は、ある日突然どこからか湧いてくるものではありません。
ほんの小さな達成感や、自分を認める気持ちの積み重ねによって、少しずつ育てていく“心の習慣”です。
最初は「5分だけ」でもいい。音読だけ、計算1問だけでもいい。
毎日その小さな一歩を続けていくことで、勉強は少しずつ日常の中に溶け込んでいきます。
あなたに今必要なのは、完璧な計画でも、長時間の勉強でもありません。
まずは小さく踏み出す一歩と、その一歩を認めてあげる気持ち。
それが、やる気を呼び起こし、次の行動へとつながっていきます。
自習室の活用で「集中できる場所」を見つけよう
「家ではなかなか集中できない」「気がついたらスマホをいじってしまう」そんな悩みを抱える中学生は多くいます。
だからこそ、学習だけに向き合える環境を意識的に整えることが、勉強を習慣化するための第一歩になります。
私たちの自習室では、そうした生徒たちが勉強に向き合いやすくなるよう、静かで落ち着いた空間を提供しています。
周囲に同じように机に向かう仲間がいることで、自分も自然と集中しやすくなり、「とりあえずやってみよう」という気持ちが生まれやすくなります。
また、教科ごとに用意されたテキスト類を活用することで、何から取り組めばいいか迷ってしまう生徒でも、手を動かしながら学習を始めることができます。
自習室という環境をうまく利用することで、勉強へのハードルがぐっと下がり、「勉強すること」自体が少しずつ日常になっていきます。
まとめ
5教科すべてが苦手というのは、言い換えれば「これからすべてを伸ばせる可能性がある」ということです。
自分に合ったやり方、自分に合った環境を見つけて、一歩一歩進んでいけば、今の状況は必ず変えられます。
「もう無理かも」と思ったその瞬間こそが、「ここから始めるチャンス」です。
勉強が苦手な自分にこそ、これからの伸びしろがある。
自習室でその一歩を一緒に踏み出してみませんか?