「中学生の子どもが、まったく勉強をしない」
「机に向かわせようとすると、すぐに不機嫌になる」
こんな悩みを抱えていませんか?
小学生の頃はそれなりに勉強していたのに、中学生になった途端に「勉強嫌い」が加速したように感じる保護者の方も多いでしょう。
実は、中学生が勉強に対して苦手意識や嫌悪感を持つのは珍しいことではありません。
しかし、ここで重要なのは「なぜ勉強を嫌うのか」という背景を正しく理解することです。
理由を見誤ったまま「勉強しなさい」と強く言っても、逆にやる気を失わせてしまうリスクもあります。
この記事では、中学生が勉強を嫌いになる主な原因を掘り下げ、それを克服するための具体的なアプローチ、さらに保護者としてできるサポートについて詳しくご紹介します。
なぜ中学生になると「勉強が嫌い」になるのか?

勉強の難易度が急に上がる
小学校では基礎的な内容が中心で、比較的「覚えれば解ける」問題が多かったのに対し、中学では科目が増え、内容も抽象的・論理的になってきます。
数学なら方程式や関数、理科では化学反応や電流など、初めて出会う概念ばかりです。
「理解できない」「教科書を読んでも分からない」という経験が続くと、次第に「自分は勉強ができない」「もうやりたくない」と感じるようになります。
成績や順位で比較される機会が増える
中学では定期テストの点数が明確に評価され、通知表や内申点にも直結します。
さらに、学校によってはテストの順位が掲示されたり、親が過剰に点数を気にしたりすることで、「人と比べられるプレッシャー」に苦しむことも。
その結果、勉強が「自分の価値を決める道具」のように感じてしまい、ストレスや不安の原因となることがあります。
思春期による感情の不安定さ
中学生は思春期のまっただ中。自我が芽生え、自分なりの考えや価値観が生まれてくる一方で、親や先生に対して反発的になりやすい時期でもあります。
「親に言われるとやりたくない」「先生に強制されると嫌になる」
このような感情は、多くの中学生が抱く自然な心の動きです。
これを理解せずに「何でやらないの?」「またスマホばかり」と注意してしまうと、かえって反発を招いてしまいます。
学び方が合っていない
実は、学習がうまくいっていない背景には「やり方が合っていない」ことが多くあります。
視覚で覚えるのが得意な子に、耳からの学習ばかりをさせても効率は上がりません。
また、長時間の詰め込み学習や、単純な暗記の繰り返しは、本人にとっては「苦痛」そのもの。
これでは「勉強=つらいもの」として脳に刷り込まれてしまいます。
勉強嫌いを克服するための4つのステップ
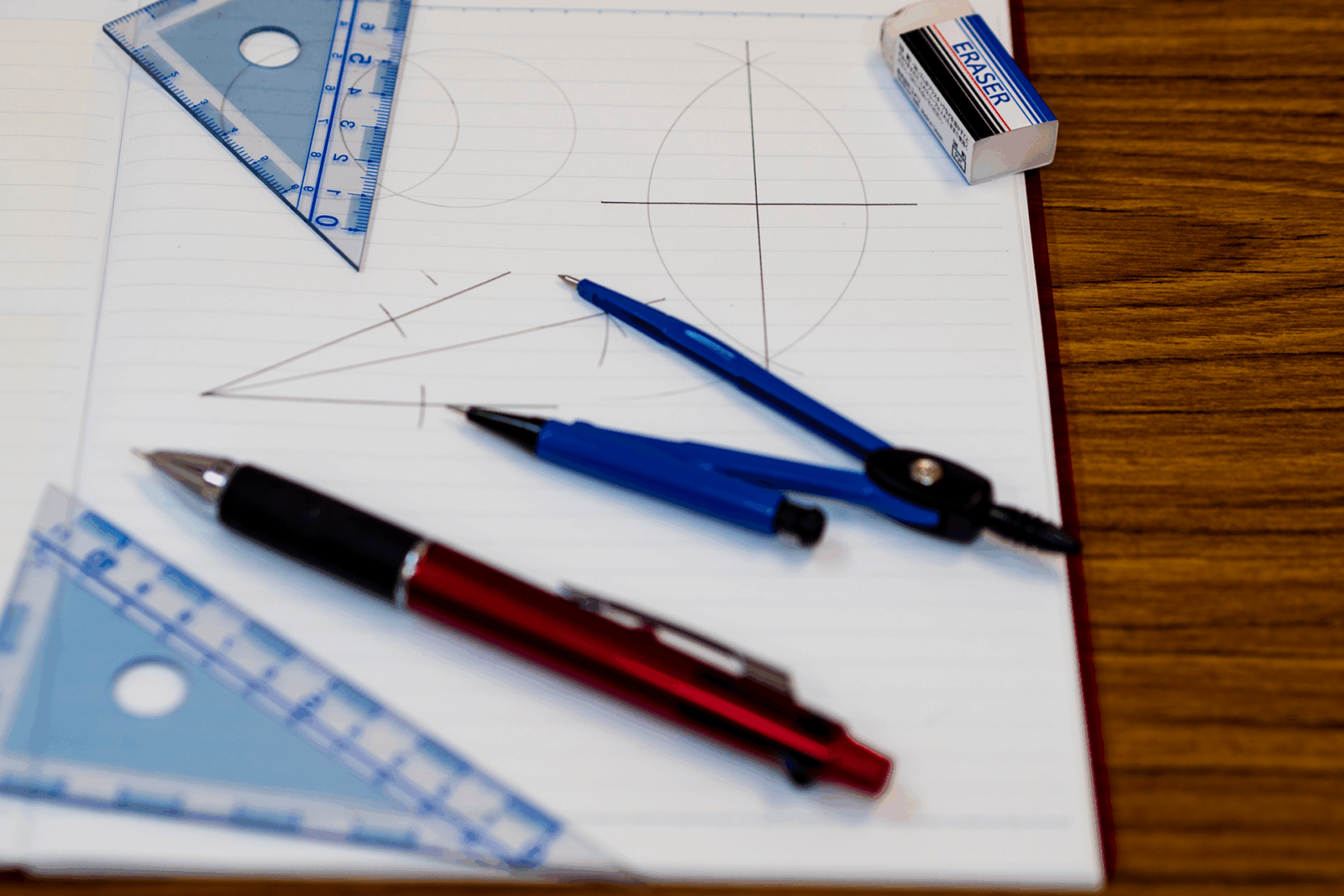
「うちの子、どうしても勉強に前向きになれない…」
そんな悩みを抱えているご家庭は少なくありません。
しかし、勉強に対するネガティブな感情は、本人の努力だけでなく、周囲の関わり方や取り組みの工夫次第で変えていくことが可能です。
ここでは、少しずつでも勉強と向き合えるようになるための4つのステップを、具体例を交えてご紹介します。
どれも今日から実践できるものばかりですので、お子さまと一緒に試してみてください。
ステップ1:まずは「できた」を増やすことから。自己肯定感を育てよう
勉強嫌いの背景には、「どうせやってもできない」「何度やっても分からない」という“自信のなさ”が深く関係しています。
これは、過去の失敗体験や叱責、成績による比較などが原因で、「勉強=つらい・自分には向いていない」と思い込んでしまっている状態です。
そこでまず取り組みたいのが、“小さな成功体験”を積み重ねて、自己肯定感を取り戻すこと”です。
たとえば
- 「今日は英単語を5つ覚えられた」
- 「数学の1問目がちゃんと解けた」
- 「いつもより10分早く机に向かえた」
このような“本当に些細なこと”でも、できた瞬間にしっかり言葉にして褒めてあげることで、本人の中に「やればできるかも」「少しずつ前に進んでる」という感覚が芽生えていきます。
ポイントは、「量」や「難しさ」を求めるのではなく、“達成の体験”にフォーカスすること。
自信を取り戻すことが、すべての第一歩になります。
ステップ2:合わないやり方はやめよう。学び方を一緒に見直す
成績が伸びないからといって、「頑張りが足りない」と責めてしまうのはNGです。
子どもにとって効果的な勉強法は一人ひとり異なります。
努力しても結果が出ない場合、多くは“やり方が合っていない”ことが原因です。
以下のような個性に注目して、本人に合った方法を一緒に探してみましょう。
▼ 学習タイプ別のアプローチ例
- 書いて覚えるのが苦手な子 → 音読・録音・リズムを使った暗記
- 集中力が続かない子 → タイマーを使った「ポモドーロ学習法」(25分勉強+5分休憩)
- 図や色で記憶しやすい子 → カラフルな図解ノートやマインドマップ
- 耳からのインプットが得意な子 → 教材の読み上げ音声、YouTubeなどの解説動画
- 動きのある学習が得意な子 → 教材の付箋を使って並べ替える、ホワイトボードに書く
また、オンライン教材やアプリも今は非常に充実しており、「ゲーム感覚で学べる」スタイルは、勉強嫌いの子どもにとって入り口になりやすいです。
何より大切なのは、「自分に合ったやり方なら少しだけ楽しく感じる」「やり方を変えたら結果が変わった」という体験をすること。
学習に対する抵抗感が自然と薄れていきます。
ステップ3:達成可能な“短期目標”を立てて成功体験を積み重ねる
「志望校に合格する」「苦手科目を克服する」といった大きな目標は、最終的には必要ですが、それだけでは日々のモチベーションにはつながりにくいものです。
特に勉強が苦手な子にとっては、遠すぎるゴールに感じてしまい、「どうせ無理」とあきらめてしまう原因にもなります。
そこで有効なのが、“短くて具体的な目標”をたくさん立てることです。
▼ 例としては
- 「今週中に英語のワークP.10〜P.15までやる」
- 「今日中に社会の用語カードを10枚だけ覚える」
- 「金曜日の漢字テストで80点以上を目指す」
- 「今夜は関数の問題を3問だけ解いてみる」
こういった「すぐ達成できそうな範囲」で目標を設定し、達成できたら「やったね!」「がんばったね!」と褒める。
カレンダーにチェックを入れる、スタンプを押すなど、“視覚的に達成を実感できる仕組み”を取り入れると、モチベーションはさらに高まりやすくなります。
成功体験の積み重ねが、やがて「学習習慣」へとつながっていきます。
ステップ4:楽しみを組み込む。“ごほうび”でやる気スイッチON!
「勉強=苦痛な時間」という意識が強い子には、“学習の後に楽しみが待っている”という体験をつくることが非常に効果的です。
大げさなごほうびは必要ありません。
日常の中でできる小さなご褒美で十分です。
▼ ごほうびの工夫例
「30分勉強したら10分だけ動画OK」
「1ページ終えたら好きなお菓子を1つ」
「1週間続けられたら、週末に好きな本を買いに行く」
「夜の学習後に、親子で一緒にボードゲームをする」
このように、“勉強をがんばったあとに嬉しいことがある”という仕組みを用意することで、子ども自身が「やる意味」を実感しやすくなります。
ただし、高価なモノを与えることが目的になってしまうと逆効果なので注意が必要です。
「ごほうびありき」ではなく、「頑張った自分への小さなプレゼント」という位置づけで活用するとバランスがとれます。
保護者ができる具体的なサポート方法

中学生の勉強嫌いを解消していくうえで、最も大きな影響を与えるのが「保護者の接し方」です。
子ども自身が自分の力で苦手意識を乗り越えていくことは理想的ですが、そのための土台として、「家庭での安心感」や「肯定的なまなざし」が必要不可欠です。
ここでは、今日から実践できる具体的なサポート方法を、子どもの心理にも触れながら詳しくご紹介します。
「勉強しなさい」は逆効果。問いかけに変えてみよう
つい言いたくなる定番のひとこと「早く勉強しなさい」。
しかしこれは、子どもにとっては命令に近く、「また言われた」「今やろうとしてたのに」と反発を生む言葉でもあります。
特に思春期の中学生は、「指示されること」に強い拒否感を覚える傾向があるため、かえって勉強から距離を置いてしまう要因にもなります。
そこで意識したいのが、“命令”ではなく“対話”による関わりです。
たとえば
- 「今日はどんな授業があったの?」
- 「どの教科が最近面白く感じる?」
- 「テスト前って不安になることある?」
このような問いかけは、子どもの内面に興味を持って接していることが伝わり、「勉強の話をしても責められない」と感じさせる効果があります。
また、日常の雑談の中で自然に勉強の話題を盛り込み、「会話の中に勉強がある」という空気感を作ることが、抵抗感の軽減につながっていきます。
点数より「努力のプロセス」に目を向けてほめる
中学生になると、テストの点数や通知表など「数値による評価」が目立ちます。
ですが、子どもにとって勉強とは本来、「理解を深め、成長していく過程」のはず。
そこを見落として点数だけで褒めたり叱ったりすると、「頑張っても褒められない」「結果が悪いと意味がない」と感じ、やる気が低下してしまいます。
たとえば、以下のような変化や努力を意識して言葉にしてみてください。
- 「前よりノートが丁寧になってきたね」
- 「わからないところをちゃんと質問できて偉いね」
- 「時間通りに始められたの、すごいよ!」
- 「自分で計画を立てようとしているのがえらいね」
これらはすべて“成果が出る前”の行動を評価している言葉です。子どもは、「結果だけじゃなく、頑張りを見てもらえている」と感じることで、次も努力してみようという意欲を持てるようになります。
「安心して勉強できる空間」を整える
学習効率を大きく左右するのが、家庭での“環境”です。
スマートフォン、テレビ、ゲーム機など、集中を妨げる要素が身の回りにある状態では、たとえ「やる気がある子」でも簡単に注意が逸れてしまいます。
そこでまず実践してほしいのは、「集中できる時間帯」と「場所」を決めることです。
- リビングではなく、静かな部屋に机を移す
- 夜ではなく、学校から帰ってすぐの時間に学習する
- 学習時間中はスマホを親に預けておく
このようなルールを“親子で一緒に”作ることで、子ども自身も納得感を持って学習に取り組みやすくなります。
さらに、机のレイアウトや文房具にも少し気を配ると効果的です。
お気に入りのペンやノート、ちょっとした観葉植物、好きなキャラクターの文具など、「この机で勉強したくなる」という気分づくりが、自然と行動のきっかけになります。
スケジュールを「共有する」姿勢が信頼関係を深める
中学生にとって、自分のペースで進めたい気持ちと、「親に管理されるのは嫌」という気持ちは常にせめぎ合っています。
そのため、「管理」ではなく「共有」というスタンスで関わるのがポイントです。
たとえば
- 「来週の提出物って何があるんだっけ?」と一緒に予定を確認する
- 「今週のワーク、どれくらい進んでる?」と進捗を聞いてみる
- 「来週のテスト、何かサポートできることある?」と伝える
このような関わり方をすれば、子どもも「見張られている」とは感じにくくなり、自主性を保ちながらも、親の存在を頼りにできるようになります。
子どもの「学びたい気持ち」を尊重する
最後に、どれだけ勉強嫌いな子でも、「本当はできるようになりたい」「認められたい」という気持ちは心の奥に必ずあります。
勉強の話題に限らず、子どもが「これが好き」「これをやってみたい」と言ったときには、できるだけ否定せず受け入れてあげてください。
たとえば
- 歴史が好きなら博物館に連れて行ってみる
- 電車や地図が好きなら社会科の学習とリンクさせてみる
- 理科の実験や図鑑が好きなら図書館で探して一緒に読む
学びと「好きなこと」がつながる瞬間に、子どもの知的好奇心は一気に広がっていきます。
それがやがて、「勉強って全部つまらないわけじゃない」という気づきにつながるのです。
まとめ
苦手を乗り越えることは、“生きる力”につながる
「勉強が嫌い」「勉強が苦手」それは今の子どもの一側面にすぎません。
大切なのは、そこで諦めるのではなく、「なぜそう感じるのか」「どうすれば変われるか」に一緒に向き合うことです。
勉強の苦手を乗り越えた経験は、やがて自分自身の成長に対する自信となり、「困難に向き合う力」や「自己解決力」につながっていきます。
焦らず、比べず、一歩ずつ。
お子さんの勉強嫌いは、きっと変えていけます。
そしてそれは、保護者の寄り添いから始まります。


